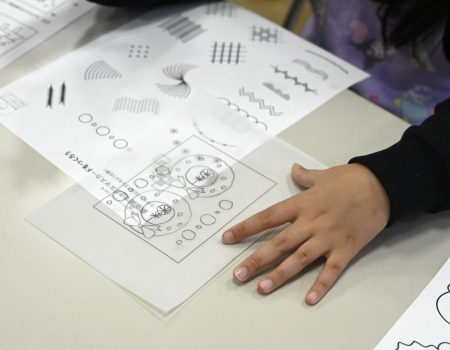-
2025年01月21日 【ワークショップレポート】新年を彩る和綴じ本をつくろう
1/13(月・祝)に、暦とあそぶワークショップ vol.27「新年を彩る和綴じ本をつくろう」(午前の部・午後の部)を開催しました。
祭事や年中行事をとおして季節を感じ、それをかたちにする暦とあそぶワークショップシリーズの第27弾。
今回は新年にあわせ、和綴じ本(仕上がりA5サイズ・1人2冊)を手づくりしました。和綴じ本(和装本)は、中国から伝来し、日本で古くから行われている装幀方法による本。
今回は和紙、でんぷんのり、麻糸、こよりといった素材を用い、「四つ目綴じ」という基本的な綴じ方で制作しました。表紙と裏表紙のほか、見返し、角布(本の背の角を包む布。今回は和紙を使用)も自分の好きな色を選びます。

-
2024年12月26日 【ワークショップレポート】しずびチビッこプログラム(キース・へリング展)
12/21(土)にしずびチビッこプログラム(キース・へリング展)を開催しました。
しずびチビッこプログラムは小さな子ども達のためのアート体験プログラム。
お子さまがプログラムを体験中、保護者の方には展覧会(今回は「キース・へリング展」)をご覧いただきます。今回は2歳から6歳の子どもたちが、キース・へリングが用いた技法や表現を参考に、シルクスクリーンでエコバックをつくりました。
はじめに展覧会出品作品をモニターで鑑賞したら、制作スタート!
キース・へリングの表現を参考に、静岡市美術館のロゴマークと、動きを表すアクションラインを配置します。

-
2024年12月18日 【ワークショップレポート】銅版画でクリスマスカードをつくろう
12/1(日)、12/8(日)に、プレゼントワークショップ vol.42「銅版画でクリスマスカードをつくろう」(子ども編・大人編)を開催しました。
今回はクリスマスにあわせ、銅版画家の武田あずみさんを講師に招き、エッチング*の技法を用いてクリスマスカードを制作しました。
*銅板等を酸で腐蝕する凹版技法の一種。表面に耐酸性の防蝕膜をつくり、その上からニードル等で膜を除きながら線を描く。腐蝕液にひたすと、膜がついていない部分が腐蝕されて凹版ができる仕組み。今回は油性ペンで描いた部分を防蝕膜とし、表面に凹みをつけるディープエッチングも行いました。
まずは下絵を描き、銅板に転写します。
-
2024年11月09日 【ワークショップレポート】しずびチビッこプログラム(「写真をめぐる100年のものがたり」展)
11/4(月・祝)にしずびチビッこプログラム(「写真をめぐる100年のものがたり」展)を開催しました。
しずびチビッこプログラムは小さな子ども達のためのアート体験プログラム。
お子さまがプログラムを体験中、保護者の方には展覧会(今回は「写真をめぐる100年のものがたり」展)をご覧いただきます。今回は2歳から6歳の子どもたちが、箱形のカメラづくりに挑戦。
感光紙を用い、撮影、現像までを行いました。 -
2024年09月08日 【ワークショップレポート】しずびチビッこプログラム(「西洋絵画の400年」展)
8/31(土)にしずびチビッこプログラム(「西洋絵画の400年」展)を開催しました。
しずびチビッこプログラムは小さな子ども達のためのアート体験プログラム。
お子さまがプログラムを体験中、保護者の方には展覧会(今回は「西洋絵画の400年」展)をご覧いただきます。今回は2歳から6歳の子どもたちが、展覧会の出品作品を立体的に表した紙のジオラマ「立版古(たてばんこ)」づくりに挑戦しました。
はじめに出品作品をモニターで鑑賞。

-
2024年04月30日 【ワークショップレポート】しずびチビッこプログラム(「細見美術館の名品」展)
4/28(土)にしずびチビッこプログラム(「細見美術館の名品」展)を開催しました。
しずびチビッこプログラムは小さな子ども達のためのアート体験プログラム。
お子さまがプログラムを体験中、保護者の方には展覧会(今回は「細見美術館の名品」展)をご覧いただきます。今回は2歳から5歳の子どもたちが、出品作品を参考に螺鈿*(らでん)や蒔絵*(まきえ)の技法に挑戦しました。
*螺鈿(らでん)…夜光貝や鮑貝などの貝殻の真珠層を切り抜き貼りつける技法。
*蒔絵(まきえ)…漆で模様を描き、その漆が乾かないうちに金粉、銀粉などを蒔き付ける技法。はじめに出品作品をモニターで鑑賞。

-
2023年08月16日 【ワークショップレポート】しずびチビッこプログラム(「さくらももこ展」)
8/5(土)にしずびチビッこプログラム(「さくらももこ展」)を開催しました。
しずびチビッこプログラムは小さな子ども達のためのアート体験プログラム。
お子さまがプログラムを体験中、保護者の方には展覧会(今回は「さくらももこ展」)をご覧いただきます。午前の部と午後の部、計18名の子どもたちが参加してくれました。今回はスクリーントーン(漫画の背景などに使われる、模様が描かれた素材)を貼って作品を制作しました。
4つのコマに絵を描いたら、背景に自分で選んだスクリーントーンを貼ります。
-
2023年05月19日 【ワークショップレポート】「親子でつくる七宝焼の贈り物」
5/13(土)にプレゼントワークショップ vol.39「親子でつくる七宝焼の贈り物」を開催しました。
家族や大切な人への想いをかたちにしたり、日々の暮らしを彩る作品を制作する「プレゼントワークショップ」シリーズの第39弾。
今回は七宝焼*でブローチを制作しました。
*七宝焼(しっぽうやき)とは、金属の表面に色とりどりのガラス質の釉薬をのせて焼き付けたもの。仏教の経典にある七種類の宝をちりばめたような美しさである、という意味で「七宝」の名がついたという。
完成見本
-
2023年02月24日 【ワークショップレポート】ひな祭りの準備をしよう!
2/18(土)に「暦とあそぶワークショップvol.24 ひな祭りの準備をしよう!」を開催しました。
祭事や年中行事をとおして季節を感じ、それをかたちにする、暦とあそぶワークショップシリーズの第24弾。
今回はひな人形の最初の形である立雛(たちびな)の例を参考にオリジナル” 立雛” をつくりました。はじめにひな祭りの歴史、様々な立雛の例をスライドで鑑賞し、それを参考に着物、襟、袴、顔などのパーツを制作しました。
-
2023年01月25日 【ワークショップレポート】節分の準備をしよう!
1/21(土)に「暦とあそぶワークショップ vol.23 節分の準備をしよう!」を開催しました。
祭事や年中行事をとおして季節を感じ、それをかたちにする、暦とあそぶワークショップシリーズの第23弾。
今回は節分の由来を学びながら、江戸時代より静岡市に伝わる鬼福(おにふく)を参考に、オリジナル鬼福*を制作しました。
*鬼福…賎機焼の特徴的な造形のひとつで、外側は鬼の形をし、内側にお多福が描かれた器のこと。
※材料は賎機焼で使用する粘土とは異なります。まずはさまざまな鬼の絵を見くらべ鬼の特徴について考えたあと、2色のオーブン陶土をのばしておわん型にし、それぞれのイメージで鬼の顔を形作りました。
HOMEBLOG