過去の展覧会
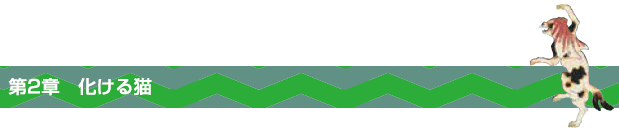
“化け猫”は江戸時代後期には歌舞伎や合巻本(絵入りの読み物)の復讐譚に欠かせない存在として登場します。文政10(1827)年、歌舞伎芝居「独道中五十三駅」で三代目尾上菊五郎が化け猫の精を演じ大評判となり、以降「化け猫物」は人気演目として繰り返し上演されました。このとき四代目鶴屋南北により創作された、老婆が夜な夜な行灯の油を舐めるという化け猫像は、江戸時代の人々が猫から連想するイメージ―1章でみてきた踊る猫や女三宮、老婆に取り憑く猫等―が集約されたものといえるでしょう。
|
|
|




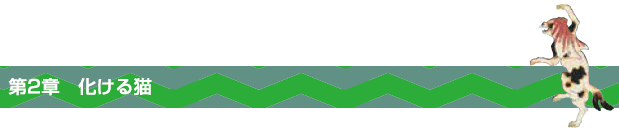
“化け猫”は江戸時代後期には歌舞伎や合巻本(絵入りの読み物)の復讐譚に欠かせない存在として登場します。文政10(1827)年、歌舞伎芝居「独道中五十三駅」で三代目尾上菊五郎が化け猫の精を演じ大評判となり、以降「化け猫物」は人気演目として繰り返し上演されました。このとき四代目鶴屋南北により創作された、老婆が夜な夜な行灯の油を舐めるという化け猫像は、江戸時代の人々が猫から連想するイメージ―1章でみてきた踊る猫や女三宮、老婆に取り憑く猫等―が集約されたものといえるでしょう。
|
|
|
