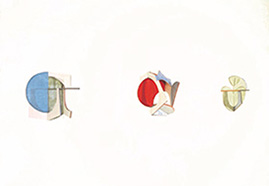映像やパフォーマンス、プロジェクトなど、表現のメディウムが拡張した今日からすると、「絵画・彫刻の復権」が謳われた1980年代の作家たちは一見保守的なように見えます。しかし彼らは、伝統的な絵画や彫刻の歴史を踏まえながらも、その形式や物質性に揺さぶりをかけ、新たな表現を追求しました。
戸谷成雄や中原浩大(エントランスホールに展示)は、木や石、粘土といった古典的な素材を用いていますが、その関心は、戸谷は彫刻の成り立ちとその表面に、中原は従来の彫刻にはない構造の軟体性やイメージの顕れへと向けられています。岡﨑乾二郎のレリーフ的な絵画作品や、中村一美の異なる3つの奥行を1つの画面に同居させた作品は、1点の作品だけでなく複数の作品同士の関係性にまで意識が向けられています。また諏訪直樹は屏風や掛け軸といった日本画の形式を引用しながら、透明感のあるアクリル絵具による動きのある筆致によって、辰野登恵子は色彩と形態、マチエールの緊張関係によって絵画を探求しました。

80年代は、若き作家たちが等身大の日常を拠りどころに、自由な表現を展開した時代でもあります。モダニズムの「大きな物語」が失墜し、世の中が消費文化に湧くなか、杉山知子は、私的な思い出や気持ちを率直に描き出し、吉澤美香は、身近な家具にドローイングを施しました。「夏休みの工作風」の段ボール作品で登場した日比野克彦の活躍は、「美術」が「アート」として日常に溶け込んでゆく80年代を象徴しています。彼らの作品は、自由奔放に描くこと、作ることの楽しさを謳歌するかのようですが、しかし改めて今から見ると、しっかりとした造型性に裏打ちされていたことがわかります。
一方で、バブル経済が絶頂に向かうなか、80年代の半ばにはひそやかな感性も準備されていました。今村源の浮遊する彫刻には、それまでの「モニュメンタル」で「求心的」な彫刻に対して、軽やかで柔らかな世界が展開されています。普段着の人物を彫刻にした舟越桂の半身像はどれも、静謐な眼差しで時代を見つめています。


(左から)《無題(テーブル)》《無題(茶だんす)》
《無題(掃除機)》《無題(三脚)》1982年
千葉市美術館蔵 撮影:木奥惠三 |
|
|

現代アートにおける「関係性」という言葉は、フランスの理論家・キュレーターのニコラ・ブリオーが1998年に刊行した著作『関係性の美学』に端を発し、今ではより広義の意味で使われています。90年代以降、観客の参画やその過程で生まれる出来事に力点を置いた「リレーショナル・アート」と呼ばれる作品が広まったことは、近年各地で開催されている芸術祭の降盛にも通じているでしょう。
しかしこうした作品のあり方は、すでに80年代、第二次世界大戦で爆撃された教会を舞台にした川俣正による「デストロイド・チャーチ・プロジェクト」や、見る者に夢想を促す松井智惠のインスタレーション、藤本由紀夫によるインタラクティブな仕掛けなどに、その萌芽を見ることができます。宮島達男のデジタルカウンターは、命の営みや時間の連続性・関係性を想起させますが、こうした一見クールな作品も、アートと社会を結び付けようとした80年代前半のパフォーマンス作品から生まれてきたものです。

モダニズムの禁欲主義が排除した「物語性」を取り戻そうとする意識は、80年代の美術において共有されていた関心事でした。具象的な人物や動物、日本古来の神話をモチーフに取り入れるなど、欧米を中心として70年代末頃から始まった新表現主義/ニュー・ペインティングに呼応するような流れが日本でも起こりました。
横尾忠則や大竹伸朗は、日々の生活にまつわる個人的な記憶や出来事を自由に作品に取り入れ、注目を集めました。また、名画に扮したセルフポートレートによって独自の美術史を批評的に編み直した森村泰昌、セルフヌードを舟形や楕円の変形カンヴァスに焼き付けた石原友明らにより、個人の物語を直截に語る「自画像」も新たな意味を帯び始めます。80年代にグラフィックデザイナーから画家へと転向した横尾も、自身の姿を繰り返し描くことで、「私」の歴史を更新していきます。彼らは自身の記憶や、世の中に流布しているイメージのアーカイヴを掘り起こすことで、私的で多層的な物語を紡ぎ出したのです。